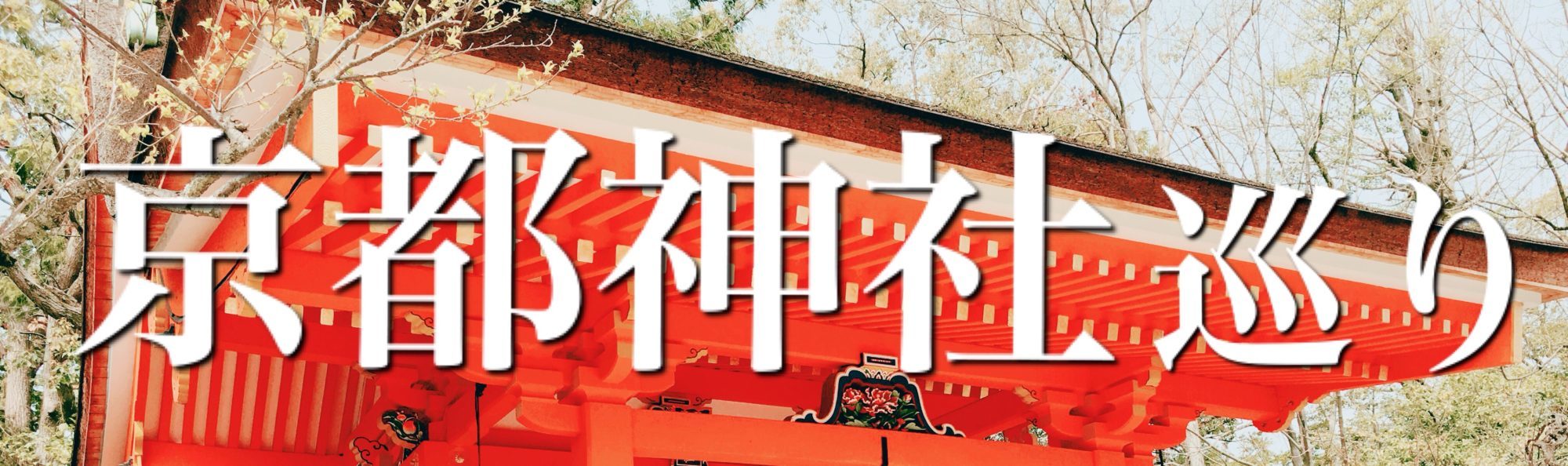平安神宮は、平安遷都1100年を記念して、明治28年に創建された、比較的新しい神社です。
歴史こそ浅いものの、高さ24m・幅18mある大鳥居をはじめ、国の重要文化財に指定されている大極殿(だいごくでん)や応天門(おうてんもん)など…見どころはたくさん。
また本殿の背後一体には、約3万平方メートルからなる広大な日本庭園「神苑」も広がっています!
今回の記事では、平安神宮を参拝する前に知っておきたい歴史・見どころについて簡単にまとめてみました!
平安神宮の歴史
平安神宮の歴史・御祭神について簡単にまとめました。
平安神宮創建の由来

(2019年9月1日 撮影)
平安神宮は、千年の都と呼ばれる京都の中では、かなり新しい神社であるといえます。
というのも、明治28年に平安遷都1100年を記念して創建された神社だからです。
歴史こそ浅いものの、創建には京都に住む人々の地元への『思い』が深く関わっています。
創建当時、古くより都として栄えた京都の衰退ぶりは酷いものでした。
幕末の動乱によって京都は戦火の中心となり、市街地は荒廃…。

その戦乱の爪痕がまだ癒えない中で、明治維新により首都は京都から東京へ遷されました。
このことが、京都の経済はもちろん、人々の心にも大きな打撃を与えたことは言うまでもありません。
そのような状況下においても、京都の人々の心が折れることはありませんでした。
『千年の都とうたわれた、京の美しい姿を後世へと受け継ぎたい』
そんな京都の人々の声が広まり、全国民からも寄付が集まりました。
平安神宮は、政府のお金ではなく…
『京都復興』を掲げた人々の援助によって創建された神社なのです!
他にも同時期、京都では、教育・文化・産業・生活などあらゆる面から復興事業が展開され、現在へと至っています。
そんな京都の復興のシンボルとなった平安神宮ですが、昭和51年(1976年)に放火による火災に見舞われます。
この放火テロ事件により、本殿・内拝殿など9棟が焼失。
平安神宮は、皇室とゆかりの深い規模の大きな神社であるため、『神宮』という最上位の社号がついています。
しかし、創建は新しかったため、文化財指定を受けておらず、国からの補助金が見込めませんでした。
ですが、その際にも全国から集められた募金によって、3年後に本殿・内拝殿が再建されています。
このように、平安神宮は『京都復興』への人々の篤い思いが込められた…
とても感動的な歴史・背景をもつ神社なのです。
平安神宮の御祭神

(2019年9月1日 撮影)
【東本殿】第50代・桓武天皇 (かんむてんのう)
【西本殿】第121代・孝明天皇 (こうめいてんのう)
平安京を造られた天皇・平安京で過ごされた最後の天皇の2柱を祀っています。
もともとの御祭神は、『桓武天皇』のみでしたが、昭和15年に『孝明天皇』も合わせ祀られました。
平安神宮の見どころ
平安神宮の見どころである
1.建築物
2.
3.時代祭
について紹介します!
平安神宮の建築物

(2019年9月1日 撮影)
安神宮は、平安京の正庁(様々な儀式を執り行う中心施設)であった朝堂院(ちょうどういん)を8分の5スケールで再現する形で創建されています。
朱色の社殿群は大変美しく、まるで平安京にタイムスリップしたかのごとく思わせてくれますよ。
当時の建物を厳密に考証して復元され、国の指定重要文化財である社殿も多いので必見です!
その1. 大鳥居
【登録有形文化財指定】

(2019年9月14日 撮影)
平安神宮の「顔」といえば、やはりこちらの大鳥居。
応天門より、約300mほど南に位置しています。
平安神宮の建立からおよそ30年後の、昭和4年に昭和天皇御大礼の記念事業として建立されました。
高さはなんと24m、幅は18mもあるんです!
実際に近くで見ると、そのスケールに圧倒されることは間違いありません。

(2019年9月1日 撮影)
非常な大きな鳥居であるため、石材や木材ではなく、鉄骨鉄筋コンクリートで建造されたとのこと。
柱の内部には、階梯(かいてい)があり、笠木(かさぎ)まで昇ることができるそうです。
その2. 応天門
【国の重要文化財指定】

(2019年9月14日 撮影)
大鳥居から北へまっすぐ進むと、平安神宮正面の門である応天門があります。
二層(2階建て)の楼門で、丹塗りがとても鮮やかです。
平安京の応天門も、碧瓦葺(みどりがわらぶき)の屋根であったそうで、そのように復元されています。
ちなみに応天門は、有名なことわざ『弘法にも筆のあやまり』の言い伝えの由来となった門なんですよ^^
応天門の屋根の下には、「應天門」と書かれた扁額(へんがく)がかかっているのですが…
その昔…平安京の應天門に掲げられていた額は、弘法大師(空海)によって書かれたと伝えられています。
その際に「應」の一画目の「点」を一つ書き忘れたことに気づき、筆を投げて点を書き加えたとか…!
面白い逸話ですよね。
その3. 蒼龍楼・白虎楼
蒼龍楼【国の重要文化財指定】

(2019年9月1日 撮影)
平安京は、四神の存在を思わせる四神相応の地に築かれました。
北は玄武(げんぶ)、東は(そうりゅう)、西は白虎(びゃっこ)、南は朱雀(すざく)に守られていたと伝えられています。
蒼龍楼・白虎楼はともに、この四神に因んだ名称であるといえます。
共に、明治28年に造営され、屋根は、四方流れ・二重5棟の入母屋造(いりもやづくり)・碧瓦本葺(みどりがわらほんぶき)が施されています。

(2019年9月1日 撮影)
東側の手水舎には、(蒼龍)がいます。
白虎楼【国の重要文化財指定】

(2019年9月1日 撮影)
白虎楼のすぐ隣は、『神苑』の入り口にもなっています。

(2019年9月1日 撮影)
西側の手水舎には、白虎がいました。
その4. 大極殿
【国の重要文化財指定】

(2019年9月1日 撮影)
大極殿(だいごくでん)は平安京の正庁である、朝堂院(ちょうどういん)の中でもメインの建築物であり…
天皇の即位礼や海外の使節との謁見などに至るまで、様々な国家的な儀式が行われていました。
正面は約30メートルの大きさです。
規模は当時の2分の1だそうですが、屋根に使用されている、碧瓦(へきがわら)は平安時代の大極殿よりも現在の方が多く使われており、豪華に復元されているそうです。
また、大極殿の前庭の左右には「左近の桜」「右近の橘」が植えられています。
左近の桜
2016年4月2日撮影 #京都 #桜#平安神宮 の桜です。神苑の桜はあと少しかかりそうですが、左近の桜は見頃だと思います。左近の桜は見頃が短いので、興味のある方は是非!https://t.co/xDYE2YGVbQ pic.twitter.com/1XQN1v04Jl
— 京都プレス || 地域密着型情報サイト (@kyotopress1) April 2, 2016
右近の橘
きのう雨が降ったから、さらに清められた感ある平安神宮。常世の国の不老長寿の妙薬「右近の橘」がみっちり実をつけてた。 pic.twitter.com/CBRZWROf4K
— さなゑ (@sanaetzk) November 22, 2017
平安神宮の庭園『神苑』
平安神宮の本殿の背後一体には、約3万平方メートルからなる広大な日本庭園「神苑」が広がっています。

(写真掲載元:京都フリー写真素材集)
東西南北四つの池を中心に、各時代の庭園形式を取り入れた池泉回遊式(ちぜんかいゆうしき)となっています。
神苑は、造園家・7代目小川治兵衛らによっておよそ20年以上掛けて作庭されました。
近代を代表する広大な日本庭園であり、昭和50年には国の名勝に指定されています。
四季折々の様々な植物が植えられているので、年間を通して楽しむことができますよ。
また、神苑を見学するには、拝観料金が必要なのですが…
6月上旬・9月19日の年に2回、無料公開されています!
(ちなみに令和元年は6月7日が無料公開日でした)
6月の無料開放日には、西神苑の白虎池周辺にて、200種2000株のが見頃を迎えます!

(写真掲載元:京都フリー写真素材集)
神苑で、特に人気の観光スポットは、東神苑にある『太平閣(たいへいかく)』
太平閣は、栖鳳池(せいほういけ)に架けられた橋殿(屋根付きの橋)なのですが…
春は、この太平閣から眺める桜が美しいと評判です。
神苑に咲く桜は約20種類300本!
その半数は紅しだれ桜だそうです。

(写真掲載元:京都フリー写真素材集)
中神苑にある蒼龍池にかかる臥龍橋(がりゅうきょう)もおすすめ。
石柱には、かの有名な戦国大名『豊臣秀吉』によって造営された三条大橋・五条大橋の橋脚が使用されているとか…!
初夏に見頃を迎える蓮の花とを配した景観が素敵です。
神苑の入口は、白虎楼のすぐ隣です。

(2019年9月1日 撮影)
神苑の拝観時間は、季節によって異なります。
【一般入場料金】
大人 600円 小人 300円
【拝観時間】
- 【3月1日~3月14日】
午前8時30分~午後5時
- 【3月15日~9月30日】
午前8時30分~午後5時30分
- 【10月1日~10月31日】
午前8時30分~午後5時※時代祭開催日は、9時30分~11時30分
- 【11月1日~2月末日】
午前8時30分~午後4時30分
拝観時間・拝観料金は変更の可能性があります。
最新情報は、平安神宮(公式HP)にてご確認下さい。
平安神宮の祭礼『時代祭』

(写真掲載元:京都フリー写真素材集)
時代祭は、毎年10月22日に開催される京都三大祭りの一つです。
平安神宮の創建・平安遷都1100年紀念祭を奉祝する行事として、明治28年に始まりました。
(2019年は、22日に皇居宮殿にて『即位礼正殿の儀』が行われるため、26日に変更)
約2,000人もの人々が1000年以上に及ぶ時代装束を身にまとい約2キロの道のりを練り歩きます。
使用される衣装や祭具は、綿密な時代考証をもとに復元された本物!

(写真掲載元:京都フリー写真素材集)
上の写真は、源義経(みなもとのよしつね)の妾である、静御前(しずかごぜん)。
時代祭では、歴史上の著名人物はもちろん、各時代の庶民の風俗も見ることができますよ。

(写真掲載元:京都フリー写真素材集)
写真は、大原女(おはらめ)さん。
大原女とは、薪などを頭の上に乗せて都で売り歩いていた京都・山城の国大原の女性たちのことです。
美しい歴史風俗絵巻をぜひその目でご覧になって下さいね!
平安神宮へのアクセス
市営バス「岡崎公園 美術館・平安神宮前」は平安神宮大鳥居のすぐ前です。

(2019年9月14日 撮影)
| 正式名称 | 平安神宮 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市左京区岡崎西天王町97 |
| 電話番号 | 075-761-0221 |
| 休日・休館 | 無休 |
| 境内参拝時間 | 6:00~18:00 (時季により変動あり)※お守り・御札・朱印受付は7:30~ |
| 神苑拝観料 | 大人:600円
小人:300円 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 平安神宮には無し (周辺に有料駐車場は有) |
平安神宮の歴史・見どころに関するまとめ

(2019年9月1日 撮影)
平安神宮は、明治28年に平安遷都1100年を記念して創建された比較的新しい神社です。
幕末の動乱、首都遷都により打撃を受けた京都を救おうとした人々の思いが形となった神社です。
平安神宮は『京都復興』のシンボルとも言えます。
そんな平安神宮は、見どころがたくさん。
高さ24m、幅18mもある大鳥居や、国の重要文化財に指定されている大極殿や応天門などの建築物。
また、国の名勝に指定されている日本庭園『神苑』は四季折々、様々な姿を見せてくれます。
日本三大祭りの一つである『時代祭』も毎年10月に開催され、およそ2000名から成る歴史風俗絵巻は圧巻です!
平安神宮周辺にある神社
平安神宮より徒歩約10分程で、岡崎神社に到着します。

京都市左京区に鎮座する岡崎神社は、近年「うさぎ神社」として女性から人気を集め…
「子授け・安産・厄除け」のご利益があることで知られています。
そんな岡崎神社には狛犬ならぬ、狛うさぎをはじめ、招きうさぎなど…うさぎだらけ!
参拝者が奉納した「うさぎみくじ」がずらりと並んだスポットは特にインスタ映えすると大人気です。
岡崎神社の御朱印に関する記事はこちら
うさぎ尽くしの岡崎神社(京都)の御朱印はもらえない?御朱印の種類・値段・授与時間は?御朱印の有無も!
岡崎神社(京都)にはうさぎの置物があるの?人気のうさぎみくじやお守りの種類・値段も紹介!
平安神宮から岡崎神社へは徒歩約10分ほどです。