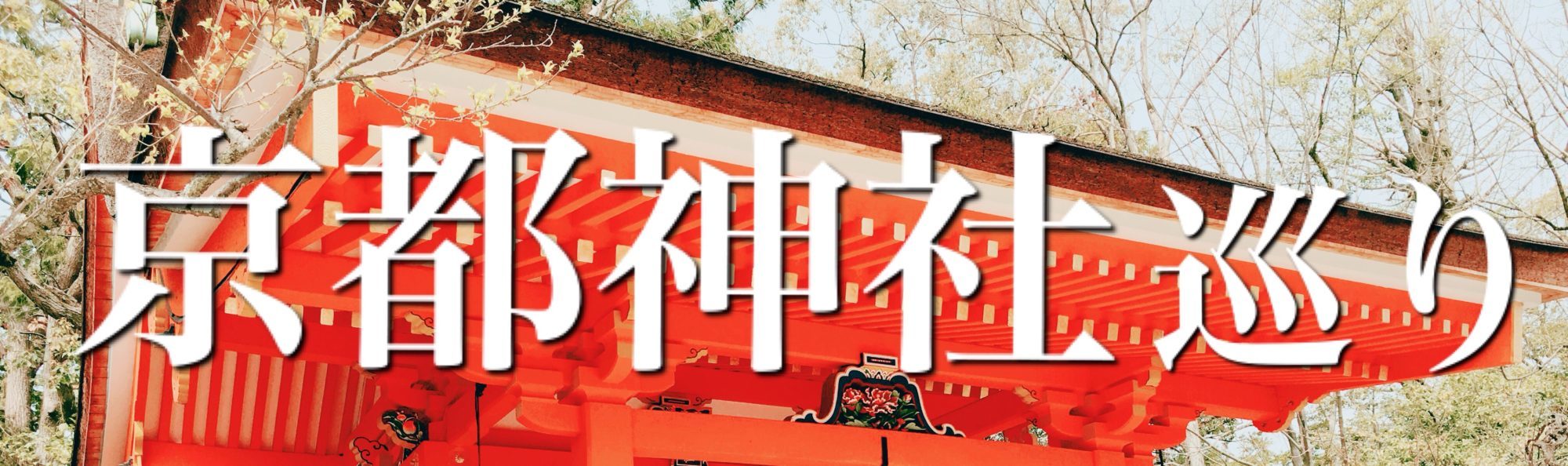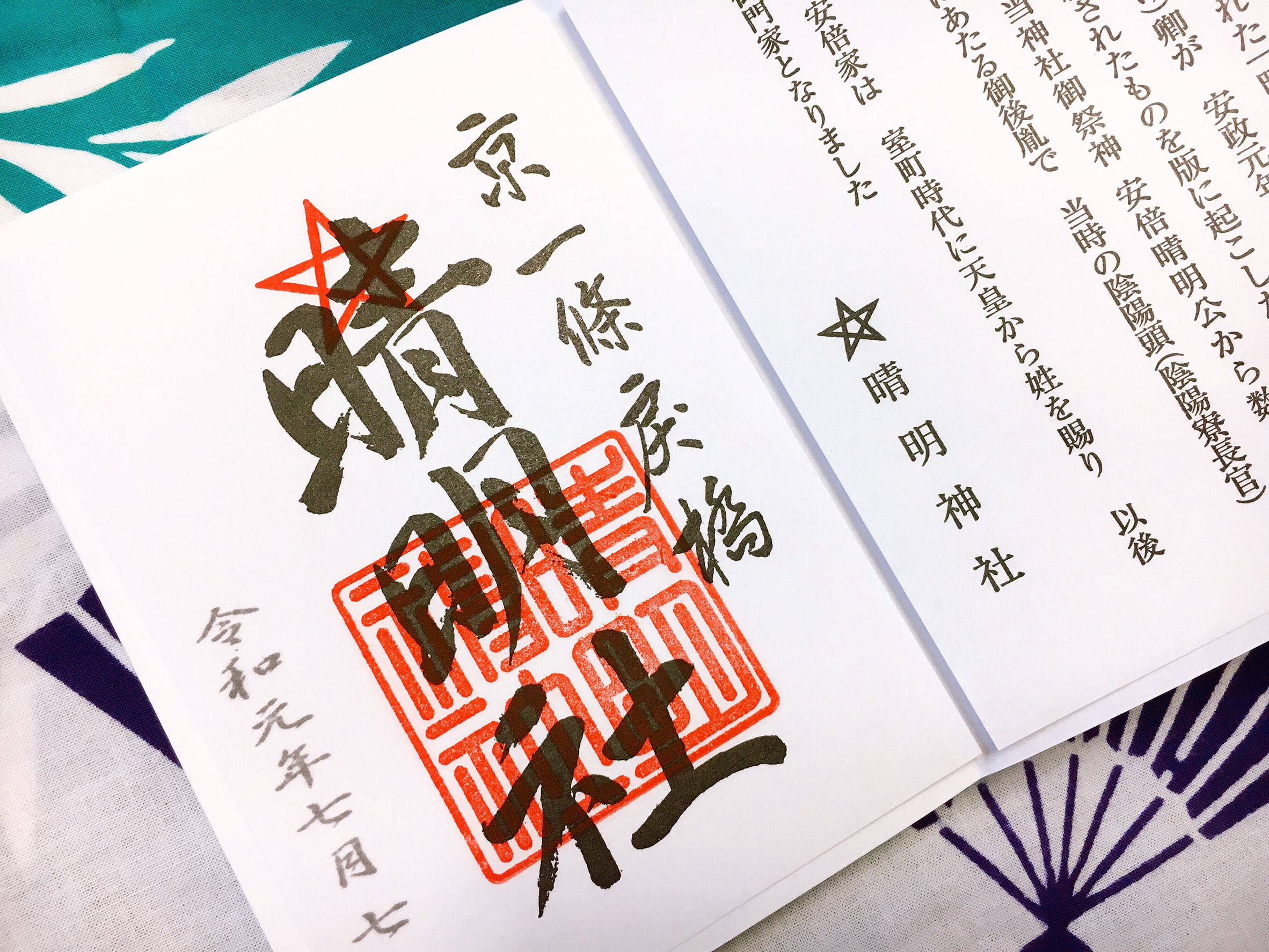伏見稲荷大社は、全国の3万社ほど稲荷神社の総本宮とされ、現在では、日本のみならず海外の方からも絶大な人気を誇る神社です。
そんな伏見稲荷大社は、約1300年のとても歴史ある神社です。
今回の記事では、参拝するなら事前に知っておきたい、伏見稲荷大社の歴史・見どころを修学旅行生の方にもわかりやすく簡単にまとめ、解説します。
御本殿や、千本鳥居、楼門、お狐さま、お塚・・・など伏見稲荷にはたくさんの魅力があります。
予備知識がある状態で参拝すれば、より充実した参拝体験ができるはず…!
伏見稲荷大社の歴史・簡単まとめ
伏見稲荷大社は、2011年(平成23年)にご鎮座1300年を迎えたとても歴史ある神社です。

(2019年12月29日 撮影)
現在までの変遷を抜粋し、稲荷信仰にも触れながら時代別(奈良時代ー明治時代)に簡単にわかりやすく紹介します。
①伏見稲荷大社の歴史ー奈良時代
伏見稲荷大社の創建については、諸説ありますが…
奈良時代・711年(和銅4)二月初午の日に、秦伊呂具(はたいろぐ)が稲荷山の三ヶ峰(みつがみね)に、稲荷大神を祀ったことが始まりであるとされています。
ちなみに、秦氏(はたし)とは、朝鮮半島から渡来し、高度な技術・経済力をもって山城国(京都府)を本拠にした一族です。
平安京の遷都以前、現在の京都府南部にあたる山城国(やましろのくに)について書かれた書物…
「山城国風土記」逸文が残されています。
秦一族の長者であった、秦伊呂具(はたいろぐ)が稲を積んで、富み栄え…
餅を弓の的にして射ようとしたところ…餅が白鳥となって飛び去った。
その白鳥が舞い降りた山の峰に稲が生えた。

これにより、その場所にお社をつくり「伊奈利 (稲生)【イネナリ→イナリ】」を社の名前とした。
稲作により国をつくってきた日本人にとって、稲や米は神様のように信仰する対象でした。
そのお米で作った餅を弓の的にするというのは、神そのものを射るということ。
つまり、なのです。
よって、お餅は白鳥となって飛び去ってしまった、というわけですね。
その白鳥が飛んでいったのが、現在の稲荷山の「三ヶ峯」とされています。
②伏見稲荷大社の歴史ー平安時代
平安時代初期になると、現在のように「稲荷(いなり)」と記されるようになりました。
また、稲荷信仰も日本全国へと広がっていきます。
それには…真言密教(しんごんみっきょう)を広めた「弘法大師(こうぼうだいし)」(空海)が大いに関係しています。

東寺での真言密教の布教を認められた空海は、東寺の守護神として稲荷神を勧誘したのです。
そして次第に稲荷神は、密教の尊格『ダキニ天』という神様と同一視(習合)されるようになっていきます。
ダキニ天は、インドにおいて「豊穣の女神」として信仰され、また人々の願いを何でも叶えてくれる神様でした。
日本においては、狐にまたがった姿で描かれたため、狐を神使とする『稲荷神』と同じ神様であると考えられるようになったようです。(諸説有り)
このようにして、もともと稲の神・農業の神であった稲荷神が、現世利益をもたらす神様として信仰され日本中へと広がっていったのです。
そして、平安時代は、稲荷大神の神様の地位がどんどん上がっていった時期でもあります。
天慶5年(942)には、なんと神社の位における最高位にあたる…
「正一位の極位」にまで上り詰めています。
また、あの清少納言も「枕草子」の中で稲荷山を登拝した旨を書き記しています。
以上のことから…
稲荷山は平安時代にはすでに、かなり知名度のある霊山になっていたことがわかります。
③伏見稲荷大社の歴史ー室町時代
細川勝元と山名宗全の勢力争いにより勃発し、約11年続いた応仁の乱。
この戦乱により、京都は焼け野原となってしまいましたが、稲荷社も例外ではありませんでした。
社殿など全てが焼き尽くされてしまったのです。
しかし、壊滅的な状態であった稲荷社を復興へと導くのに大きな役割を果たしたのが…
「稲荷勧進僧(いなりかんじんそう)」「稲荷行者」といった人たちです。
稲荷社の御神徳・霊験などを説きながら、諸国を練り歩き、社殿の造営や修復などの寄付を募ったのです。
彼らの活躍のおかげもあり、修繕費用も捻出され…
社殿焼失から約30年後、1499年(明応8年)には、現在のご本殿が再興されました。

(2019年5月21日 撮影)
また、1589年(天正17年)、安土桃山時代には豊臣秀吉によって楼門が寄進・再建されました。
④伏見稲荷大社の歴史ー江戸時代
江戸時代になると、稲荷信仰が、社会の発展に応じて特に江戸を中心に爆発的な流行を見せます。

理由の一つには、人々の中でもっぱら『狐=稲荷神』と認識されるようになったことがあげられます。
また流行にともない、さらに様々なご利益も求められるようになりました。
大名・旗本などの武士が稲荷を屋敷神としてまつり、「無病息災・子孫繁栄」を願ったり…
江戸の町家の発展にともない、「商売繁盛」のご利益も期待されるようになりました。
ちなみに、伏見稲荷大社の千本鳥居の奉納は、江戸時代末期にはじまり、盛んになっていったのは近代以降です。
⑤伏見稲荷大社の歴史ー明治時代
そして、明治時代になると、かつて神様が降臨し祠などがあった場所を指す「神蹟」が…
7つ確定され(七神蹟)その親塚が建立されました。
これが契機となって「お塚信仰」というものが盛んになります。
これは、各個人がご神徳に因んだ神名やそれぞれの家で祀っている“○○稲荷大神”の神名を、石に刻んで、お山に奉納したことをいいます。
お塚の数は、昭和初期には約2500基、昭和40-41年に行われた調査では、7762基あったと報告されていますが…
現在では、1万基を超えるといわれています。
つまり、現在の稲荷山の神秘的な景観が作られるようになったのは、伏見稲荷の長い歴史を思えばつい最近のことであると言えますね。

(2019年5月21日 撮影)
- 「稲荷大神」:中村陽 監修
- 日本の信仰がわかる神社と神々:かみゆ歴史編集部 編著
伏見稲荷大社の神様とご利益
伏見稲荷大社に祀られている神様・ご利益を紹介します。
【主祭神】
■宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)
【その他御祭神】
■田中大神(たなかのおおかみ)
■佐田彦大神(さたひこのおおかみ)
■大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)
■四大神(しのおおかみ)
ご利益:商売繁盛・五穀豊穣
他にも家内安全・交通安全・芸能上達・安産・万病平癒・学業成就・・など
伏見稲荷大社は、「商売繁盛・五穀豊穣」だけでなく…
多彩なご利益があるとされ、人々の生活に密着した神様として親しまれています。
伏見稲荷大社の見どころ・簡単まとめ
伏見稲荷大社の参拝前に、知っておきたい見どころを紹介します!
事前に知っておくと、より参拝を楽しむことができますよ。
修学旅行生の方にもわかりやすく簡単にまとめていますので、是非目を通してみてくださいね。
- お狐さま(狐像)
- 豊臣秀吉が造営「楼門」
- 稲荷造りの「ご本殿」
- 千本鳥居
- 占い石のある「奥社奉拝所」
- 神秘のお山巡り「稲荷山」
以上の順に紹介します。
お狐さんがいっぱい!?
伏見稲荷大社には、あらゆるところにたくさんのお狐さま(狐像)が見られます。

(2019年12月29日 撮影)
なぜなら…お狐さまが、伏見稲荷大社の神様の使い…つまり(眷属けんぞく)であるからです。
神様そのものではないことに注意です!
狐は神使とされた理由は…
- 狐の尻尾がみのる稲穂を連想させた
- 狐の外見や習性が神的な存在を思わせた
- 水田によく出現することから、田畑の守護神と考えられた
- 食物神である御けつ神から『三狐(ミケツ)』が連想された
など諸説あります。
ちなみに、狐像は作られた時代によって表情も様々。

(2019年12月29日 撮影)
いろんなお狐さまを見てみてくださいね!
また、ほとんどのお狐さまが、『鍵・玉・稲・巻物』など様々なモノをくわえているのですが…
もちろん、それぞれちゃんと意味があってのことです。
↓『お狐さまがくわえているモノ』の意味についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
伏見稲荷大社は、全国に30,000社程ある稲荷神社の総本宮として、今では日本のみならず海外からも絶大な知名度、人気を誇る神社です。 そんな『伏見稲荷大社』の境内には、あちこちにお狐さまがたくさん!! 玉や鍵、巻物をくわえ …
楼門ー豊臣秀吉により造営
伏見稲荷大社の楼門は、神社の楼門としては最大級の大きさ(幅約10m、高さ約15m)を誇ります。

(2019年12月29日 撮影)
この楼門は、天下統一を成し遂げた、かの有名な戦国大名『豊臣秀吉』によって造営されたもの。
病に伏せる母親ののため、秀吉は、伏見稲荷大社に願文(命乞いの願文)を送りました。
「母、大政所の病が治れば、一万石を神仏に寄付する」
そして…見事祈願が成就した秀吉は、そのお礼としてこの楼門を建造したのです。

(2019年12月29日 撮影)
1589年に造営されたこの楼門は、永久保存を目的として、昭和48年に大規模な解体修理がなされました。
その際に、楼門の古材から「天正17年」の墨書が発見されたとのこと。
歴史を感じますね。
楼門の左右には、随身像(ずいじんぞう)が据えられています。

(2019年12月29日 撮影)
宮中でいう、衛士(警護にあたる兵士・武士)にあたります。
御本殿ー建築様式に注目!
伏見稲荷大社の御本殿は、国の重要文化財に指定されています。

(2019年12月29日 撮影)
注目したいのは、御本殿の構造!
側面を見てみると…屋根の前面が長く、庇(ひさし)のようになっており、美しい曲線を描いています。

(2019年12月29日 撮影)
この建築様式は、『打越し流造(うちこしながれづくり)』別名『稲荷造り』とも呼ばれています。
また、軒下の桃山時代をおもわせる豪華な彫刻も必見です。

(2019年12月29日 撮影)
神使の白狐も見られます。
こちらの御本殿には、主祭神である『宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)』をはじめ…
他にも4柱もの神様が祀られています。
ちなみに『稲荷大神』とは、5柱の神々を総称した呼び名のことをいいます。
千本鳥居ー実は千本じゃない!?
伏見稲荷大社の代名詞ともいえるのが「千本鳥居」

千本鳥居とは、「奥宮(おくみや)」から「奥社奉拝所(おくしょほうはいしょ)」への山道に密集して建てられている鳥居のことをさします。
ちなみに、「千本鳥居」の「千本」とは「数えられないくらい多い」という意味で、1000本あるというわけじゃないんです!
意外と知られていませんよね。
また、これらの鳥居は全て奉納されたもの。
願い事が「通る」、または「通った」というお礼の意味から江戸時代以降に始まったとか…。
そして、千本鳥居の色といえば、鮮やかな『朱色』
朱色は、古代より魔除けを意味する神聖な色ともされています。

(2019年12月29日 撮影)
特に、稲荷神社の建造物に用いられるこの色は五穀豊穣を意味し『稲荷朱』とも呼ばれます。
隙間なく連なる朱塗りの鳥居は、参拝者を日常と切り離し異世界へと誘ってくれます。
ちなみに、千本鳥居は右側通行です。

(2019年12月29日 撮影)
間違えないようにしましょうね。
↓千本鳥居の由来や本数、奉納値段など、千本鳥居に関するあらゆる情報はこちらの記事で詳しく紹介しています。
全国に約30,000社はあるといわれる『お稲荷さん』 その総本宮として知られる『伏見稲荷大社』には日本のみならず、今や海外でも有名な鳥居があります。 そう、『千本鳥居』です。 参拝せずとも、写真やテレビその他メディアを通 …
奥社奉拝所ー占い石・おもかる石も!
奥社(おくしゃ)は、別名「奥の院」とも呼ばれており「千本鳥居」を抜けると到着します。

(2019年5月19日 撮影)
社殿の背後に、稲荷神が降臨したと伝えられる『稲荷山 三ケ峰』が位置していることから…
『お山の奉拝所』とされ、願望成就の祈願所として、多くの人が訪れます。
社殿背後には、たくさんの小さな鳥居が奉納されています。

(2019年12月29日 撮影)
狐の顔を自由に書ける白狐絵馬も奉納されているのですが、いろんな顔があって面白いです。

(2019年12月29日 撮影)
また、奥社奉拝所限定のお守りもあるので、御本殿近くの授与所だけでなく、奥社授与所も要チェックです。
占い石として有名な「おもかる石」は、拝所右奥にあります。

(2019年12月29日 撮影)
とても人気があり、行列ができることもしばしばです。
- まず願い事をしましょう
- 石を持ち上げる前に『石の重さ』を想像します
- 石を持ち上げた際、想像よりも軽ければ願いが叶うといわれています
稲荷山ー神秘のお山巡り!
伏見稲荷を参拝したなら、ぜひおすすめしたいのが、稲荷山の登拝「お山巡り」です。※山頂までの所要時間は2時間のため、集合時間がある修学旅行生の方の登拝は厳しいかもしれません

(2019年5月21日 撮影)
お山巡りとは、稲荷山の山頂にあたる「一ノ峰」を目指して、神様をお参りしながら山を登ること。
往復距離は約4キロ、所要時間およそ2時間の道のりです。
稲荷大神の降臨地とされる稲荷山には、7つの神蹟・約一万基ものお塚があると言われ…
裏パワースポットとして大変人気があります。

(2019年5月19日 撮影)
ちなみにお塚は、稲荷神に別称を付け信仰する人々が石碑にその名を刻んで奉納したもので…
ほとんどは明治時代以後に設置されたものだそう。(記事前半で紹介)
山頂までの道のりには、お茶屋さんも数多くあるので、休憩しながらお山めぐりを楽しむことができます。

(2019年12月29日 撮影)
「それでも山頂まで行くのはしんどいし、時間もない!」
という方には山頂までの半分の距離『四ツ辻』までの登拝がおすすめ。

(2019年12月29日 撮影)
四ツ辻は、京都市中を見下ろせる絶景スポットとなっているので、まるで山頂まで登拝したような気分を味わえます。
↓お山巡り前に知っておきたい、お役立ち情報(所要時間・ルート・見どころ・お茶屋さん情報)は、こちらの記事にまとめました。
伏見稲荷大社は、全国の稲荷神社の総本宮とされ、多くの参拝客で賑わいます。 その伏見稲荷大社ですが、本殿から奥社までの参拝だけではもったいないんです。 なぜなら、稲荷山には7つの神蹟があり約一万基ものお塚があると言われ、こ …
伏見稲荷大社へのアクセス

| 正式名称 | 伏見稲荷大社 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草藪之内町68 |
| 電話番号 | 075-641-7331 |
| 拝観時間 | 終日参拝可能 |
| 交通 | ・JR奈良線 『稲荷駅』下車 徒歩すぐ
・京阪本線 『伏見稲荷駅』下車 東へ徒歩5分 ・京都市バス南5系統 『稲荷大社前』下車 東へ徒歩7分 |
| 駐車場 | あり |
伏見稲荷大社の歴史・見どころに関するまとめ

(2019年12月29日 撮影)
伏見稲荷大社は、諸説あるものの、奈良時代・711年に、秦伊呂具(はたいろぐ)が稲荷山の三ヶ峰(みつがみね)に、稲荷大神を祀ったことが始まりであるとされ…
約1300年もの歴史ある神社です。
室町時代には、応仁の乱に巻き込まれ社殿が焼失、壊滅的な被害を受けるも…
稲荷大神を信仰する人々の思いが大きな力となり、見事社殿も再建され、現在に至ります。
伏見稲荷大社の代名詞ともいえる「千本鳥居」をはじめ、国の重要文化財に指定されている「楼門」
「御本殿」など見どころたくさん!
神様の使いであるお狐さま(狐像)にも注目です。
魅力がいっぱい詰まった「伏見稲荷大社」ぜひ訪れてみてくださいね!